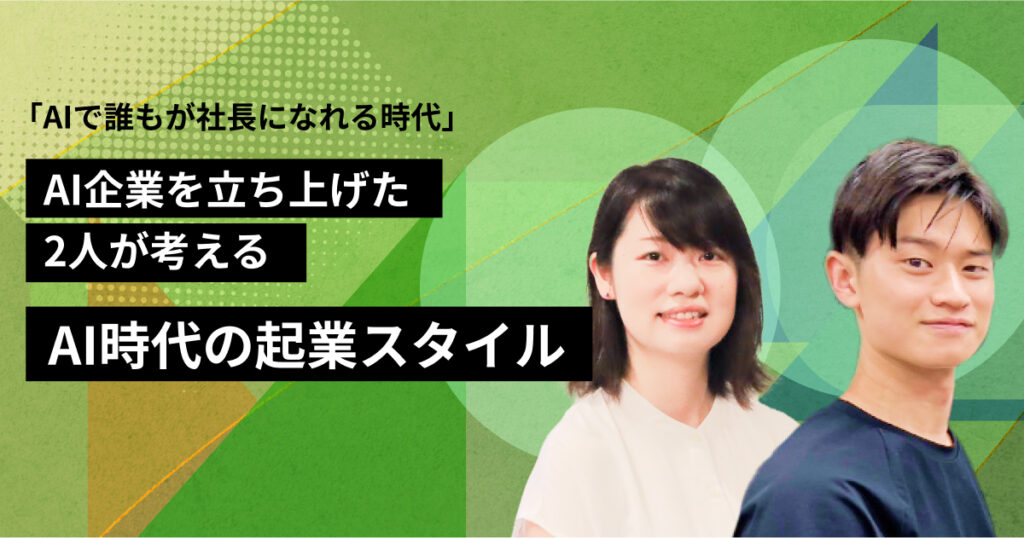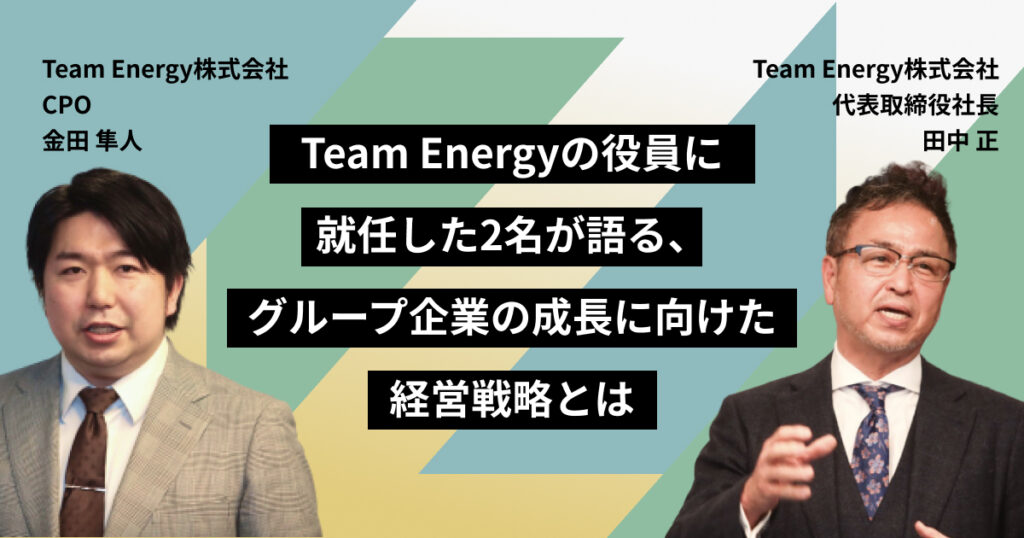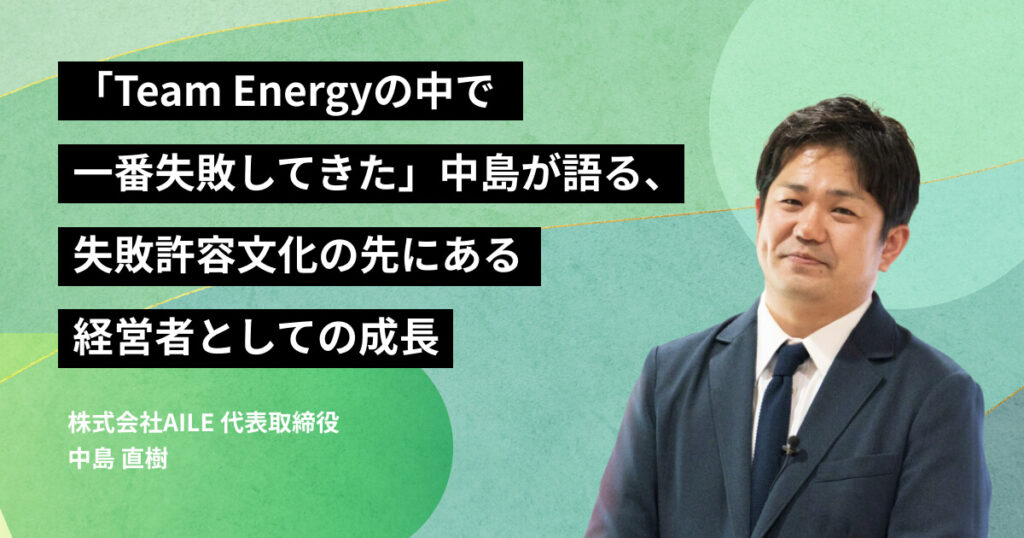目次
AIがもたらす社会変革の波は、今やビジネスや教育の現場だけでなく、日常生活にも浸透しつつあります。この激動の時代において、Team Energy AI総研はAIの力を最大限に引き出し、新たな価値を創造する使命を担っています。
Team Energy AI総研の代表取締役に就任した栗須俊勝さん。経営者としての豊富な経験と、挑戦を続けてきた独自の視点を武器に、どのようにAI事業を展開しようとしているのか。その戦略とビジョン、そして栗須さん自身の人となりに迫ります。

プロフィール
1969年福岡県生まれ。大牟田高校駅伝部で鍛え、大学院では遺伝子工学修士取得。27歳から起業、収益事業として鍵扉工事事業を展開しつつ、社会貢献事業として英語学童保育事業、関西学生起業団体「ポーターズ」を設立。近年はAI導入支援や複数のAI関連企業で役員を務め、一般社団法人AIDXリスキリング協会設立、365日AI勉強会開催などに取り組む。2024年5月にTeam Energyグループにジョインし、その後Team Energy AI総研株式会社 代表取締役に就任。
経営の転換点と得た教訓

栗須さんが経営する株式会社アサヒプロテクトニーズは、関西で「鍵の会社」としてトップ3に名を連ねるまで成長しました。その背景には、事業の転換や失敗から得た教訓があります。
BtoBに特化した戦略的転換
栗須さんが会社を創業したのは約20年前。当初はBtoCの鍵サービスを展開し、一般顧客に向けた鍵の修理や交換を主な業務としていました。しかし、電話帳広告からインターネット集客への移行期において、BtoC市場の限界を感じるようになります。
「BtoCの鍵サービスは、一生のうちに鍵を交換する経験が一度あるかどうか。それに対し、不動産管理会社などのBtoBの顧客は、毎週のように鍵交換や修理のニーズが発生します。この継続的な需要に注目し、事業をピボットする決断をしました。」
BtoBへの特化は事業拡大の大きな転機となりました。不動産管理会社やセコムとの提携を通じて、継続的で安定した案件を確保。これが、関西の鍵業界でトップクラスの企業として成長する原動力となりました。
試練と挫折からの学び
一方で、経営者としての道のりは平坦ではありませんでした。過去には社員の引き抜きにより、3分の1の社員が一度に辞めるという事態が発生。
「社員が辞めただけでなく、お客様まで持っていかれました。そこからはクレーム対応の日々。自分の経営不足を痛感しました。」
また、新規事業として飲食事業や福祉事業にも取り組みましたが、それらは失敗に終わり、多額の損失を出したといいます。
「飲食事業や福祉事業は自分の専門外でした。それなのに、十分なリサーチをしないまま軽い気持ちで参入してしまったのが大きな失敗でした。」
これらの苦い経験が、栗須さんの経営スタイルに大きな影響を与えました。
失敗から学んだ教訓のひとつは、「経営者一人で全てを抱え込むべきではない」ということです。
「以前は自分一人で判断し、指示を出していました。でも、特に専門外の分野では、信頼できる人に任せるべきだと気づきました。責任者やチームと共に考え、意思決定を下すことで、失敗を防げるようになりました。」
AIとTeam Energyとの出会いが切り拓く、新たな挑戦

栗須さんがTeam Energy AI総研の代表取締役に就任した背景には、AIとの出会いと、自分では実現が難しいことをTeam Energyの環境なら実現できるという可能性を感じたことが大きく関わっています。
AIへの関心と学びへの取り組み
栗須さんがAIに強い関心を抱いたのは、2023年3月にChatGPTを初めて体験したことがきっかけでした。AIが自動で文章を生成する様子を目の当たりにし、その技術の可能性を直感的に理解したといいます。この経験から、AIがもたらす変化をより多くの人に伝えたいという思いが生まれました。
「ChatGPTを初めて使ったとき、これが今後の生活やビジネスを大きく変える技術になると確信しました。もっと多くの人にAIを知ってもらいたいと思うようになりました。」
また、AIだけでなく、英語などの興味を持った分野を独学で深めてきた経験が、今回のAIへの取り組みにも活かされています。
「自分が興味を持ったことは徹底的に学ぶのが私のスタイルです。それが、どんな新しい挑戦においても自分を支える力になっています。」
Team Energyとの出会いとその魅力
栗須さんがTeam Energyへのジョインを決めたのは、この環境が持つ独自の魅力に可能性を感じたからです。創業初期の社長から上場企業の社長まで、多様なメンバーが集うTeam Energyの環境は、新たな視点やアイデアを得る上で理想的な場となっています。
「Team Energyは、異なる立場や経験を持つ多くの人が集まっており、その中で刺激を受けながら学び合えるのが素晴らしいところです。」
さらに、事業のスピード感が非常に早いことも、栗須さんにとって大きな魅力でした。
「Team Energyに参加してから、自分一人では難しかったことが次々と形になっていくのを実感しています。このスピード感がある環境にいられることは本当にありがたいです。」
まほろばAIコミュニティとスケールAIの取り組み

Team Energy AI総研は、AIを活用した新たな事業展開の中心として、Team Energyグループの成長を支えています。また、AI技術を誰もが身近に学び、活用できる環境を整えることを目指しています。
まほろばAIコミュニティの事業展開
2025年に向けて、Team Energy AI総研は「新規のグループ会社を15社創出する」という目標を掲げており、その社長候補者たちにはAIを学んでもらうことが必須とされています。この取り組みの一環として、AIを日常的に学べるプラットフォームの構築を進めています。このプラットフォームは、学びを通じて得た知識を実践に結びつける仕組みが特徴です。
Team Energy AI総研が運営する「まほろばAIコミュニティ」では、学んだ受講者がAI研修の講師として活躍できるプログラムも用意されています。現在、無料登録者数は1,000人に達しており、今後はこの登録者を有料会員へと転換することが目標です。
「学んだ知識を他の人に伝えられるようになることが、本当の意味での学びの完成だと思っています。まほろばAIコミュニティでは、そうした循環型の学びの場を提供していきます。」
株式会社スケールアイとのジョイントベンチャー
Team Energy AI総研は、スケールアイとのジョイントベンチャー「スケールAI」を通じて、さらなる事業展開を図っています。このスケールAIは現在、毎月200人の新規入会者を獲得しています。この勢いは2025年以降も加速すると見込まれており、毎月300〜400人規模の新規入会が期待されています。
スケールAIでは、スケールアイが英会話事業で培ったノウハウを活かし、AI教育の展開を進めています。さらに、Team Energy AI総研はスケールAIの教材制作やウェビナー運営を支援するなど、重要な役割を担っています。
「スケールアイと協力することで、私たちがAI教育の可能性をさらに広げられると確信しています。」
まほろばAIコミュニティとスケールAIは、それぞれ異なるターゲット層を持っています。
まほろばAIコミュニティは主に若年層をターゲットにしており、オンライン形式とスクール形式を組み合わせた柔軟なアプローチを採用しています。一方、スケールAIは比較的高齢の層を対象に、完全オンライン形式でサービスを提供しています。このように、両者が重複しない形で市場を開拓している点が大きな特徴です。
日本全体のAI普及を目指して

栗須さんの夢は2つあります。1つは、グループ内から上場企業を生み出すこと。
「Team Energyのネットワークを活用して、上場を目指すプロジェクトが始まっています。自分一人では難しかった夢が、今は現実味を帯びています。」
栗須さんの描くもう一つの夢は、AI教育を通じて多くの人に新しいスキルを提供し、日本全体でのAI普及を実現することです。その中で、まほろばAIコミュニティやスケールAIの事業は重要な役割を担っています。これらの活動が拡大することで、栗須さんが目指す「より多くの人にAIを学んでもらう」という夢が一歩ずつ現実に近づいています。
「AIを学ぶことで、自分の可能性を広げたり、新しい挑戦をして自己実現を果たす人をどんどん増やしていきたい。それが日本全体のAI普及につながると信じています。」
さらに、栗須さんはAI教育だけにとどまらず、多くの経営者を育てることにも情熱を注いできました。若手経営者の会やAI勉強会を自ら立ち上げ、多様な人材が互いに学び合う場を提供してきた経験は、Team Energyの社長を増やすというミッションにも大きく貢献しています。
「たくさんの経営者を育てたいという思いは昔からあります。これまで若手経営者の会や勉強会を運営してきたのもその延長線上です。Team Energyの社長を増やすという目標にも、非常にフィットしていると感じています。」
AIで挑戦を支え、次世代リーダーを育てる栗須さんの想い
「人の挑戦を支え、共に成長する」という姿勢を大切にする栗須さん。その言葉には、自らが経験を通じて築き上げてきた信念が込められています。特に社長候補者には、「AIを通じて新しい価値を創造する喜びを感じ、一歩を踏み出してほしい」という想いを語ります。
「AIの可能性に触れ、学び続けることで、次世代を担うリーダーとして自分の可能性を切り開いてください。」
栗須さんの取り組みは、Team Energy AI総研を通じて着実に広がりを見せています。そのビジョンと実直な行動は、AI事業の可能性を探るだけでなく、多くの人々に新たな学びや挑戦へのきっかけを提供しています。
これからも、Team Energy AI総研が社会にどのような価値をもたらしていくのか、ぜひ注目してください。